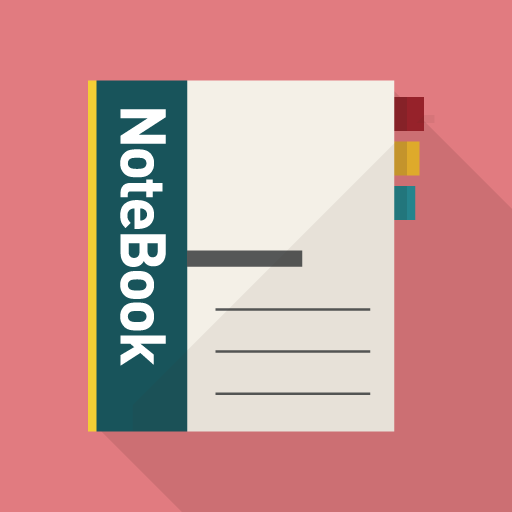その小さな口から、薬が飛び出す。あなたは、どうすればいいか迷っていませんか?
熱を出してぐったりしている我が子に、やっとの思いで薬を飲ませようとしたら、口からブーッと吐き出されてしまった。
「なんで飲んでくれないの…!」
「このままだと、病気が治らないんじゃないか…」
子どもの薬の飲ませ方は、親にとって本当に悩ましく、そしてストレスを感じる場面ですよね。どうすればいいのか分からず、一人で抱え込んでいませんか?
こんにちは!3人の娘たちの子育ての中で、数えきれないほどの薬の飲ませ方バトルを経験し、その度に試行錯誤を繰り返してきた、現役ママナースの皐月です。
お伝えしたいのは、子どもが薬を嫌がるのは、決して「わがまま」ではありません。 それは、薬の味や匂い、形状への抵抗感や、何をされるか分からない不安からくるものです。そして、親のちょっとした工夫で、薬をスムーズに飲ませられるようになる可能性は十分にあります。
この記事では、そんなあなたの不安を解消するために、嫌がる子への薬の飲ませ方のコツ、年齢別の工夫、そして注意点まで、専門家の視点と実体験を交えて、徹底的に解説します。
さあ、今日から薬の飲ませ方バトルを卒業し、お子さんの回復をスムーズにサポートしましょう。
なぜ?どうして?子どもが薬を嫌がる主な理由
子どもが薬を嫌がるのには、ちゃんとした理由があります。その理由を知ることで、適切なアプローチが見えてきます。
1.薬の味や匂い
- 子どもは大人よりも味覚が敏感です。薬の苦味や独特の匂いを不快に感じ、嫌がることが多いです。
2.何をされるか分からない不安
- 特に乳幼児は、何をされるのか分からず、口の中に異物を入れられることに恐怖を感じることがあります。
3.過去の嫌な経験
- 以前に薬を飲んで吐いてしまった、無理やり飲まされたなど、過去の嫌な経験がトラウマになっていることもあります。
4.形状への抵抗感
- 粉薬が口の中に残る、錠剤が大きくて飲みにくいなど、薬の形状が飲みにくさの原因になることもあります。
<ママナースの視点>
子どもが薬を嫌がるのは、ごく自然なことです。無理強いすると、かえって薬嫌いを助長したり、親子の信頼関係を損ねたりする可能性があります。焦らず、工夫して飲ませるようにしましょう。
【年齢別】子どもの薬の飲ませ方、成功のコツ
子どもの発達段階に合わせて、薬の飲ませ方を工夫しましょう。大切なのは、一貫した態度で、根気強く対応することです。
0歳〜1歳頃:ミルクや少量の水に混ぜる
- 粉薬:
- 少量の水で溶いてペースト状に: スプーンの背などで少量の水(数滴)で溶いてペースト状にし、清潔な指で上あごや頬の内側に塗ってあげましょう。すぐにミルクや母乳を飲ませると、薬が流れていきます。
- ミルクに混ぜる: 少量(10〜20ml程度)のミルクに溶かして、哺乳瓶やスプーンで飲ませましょう。ただし、ミルクの味が変わるのを嫌がる子もいるので、少量で試しましょう。ミルク全量に混ぜるのはNGです。飲み残すと、薬の量が分からなくなってしまいます。
- シロップ:
- スポイトやシリンジで: 頬の内側に沿って、少しずつ流し込みましょう。一気に飲ませるとむせることがあります。
- 少量の水で薄める: 味が濃い場合は、少量の水で薄めても良いでしょう。
1歳〜3歳頃:好きなものに混ぜる・ご褒美を活用
- 粉薬:
- 少量の水で溶いてペースト状に: ヨーグルト、アイスクリーム、プリン、ジャム、チョコレートシロップなど、子どもの好きなものに混ぜて飲ませましょう。ただし、薬によっては混ぜてはいけないものもあるので、薬剤師に確認しましょう。
- 服薬ゼリー: 薬を包み込んで飲ませる専用のゼリーです。味がついていて、子どもが飲みやすいように工夫されています。
- 錠剤・カプセル:
- まだ難しい時期ですが、細かく砕いて粉薬と同様に飲ませるか、服薬ゼリーで包んで飲ませましょう。
- ご褒美: 薬を飲めたら、「飲めたね!すごい!」とたくさん褒めてあげたり、シールを貼ってあげたり、好きな遊びを少しだけさせてあげたりと、ご褒美を用意するのも効果的です。
3歳〜小学生:自分で飲む練習と、理由を伝える
- 自分で飲む練習: コップで水を飲む練習をさせながら、薬も自分で飲めるように促しましょう。錠剤の場合は、口に水を含んでから薬を入れ、上を向いて飲む練習をさせると良いでしょう。
- 理由を伝える: 「このお薬を飲むと、早く元気になれるよ」「熱が下がるよ」など、なぜ薬を飲む必要があるのか、子どもが理解できる言葉で伝えましょう。
- 選択肢を与える: 「スプーンで飲む?それともコップで飲む?」など、子どもに選択肢を与えることで、自分で決めたという気持ちになり、スムーズに飲めることがあります。
【ママナースの視点】薬を飲ませる際の注意点
1.自己判断で混ぜない
- 薬によっては、混ぜると効果が落ちたり、苦味が増したりするものがあります。混ぜる際は、必ず薬剤師に確認しましょう。
2.薬の量を守る
- 医師から指示された量を必ず守りましょう。勝手に量を減らしたり、増やしたりするのは危険です。
3.使用期限を守る
- 薬には使用期限があります。期限切れの薬は使用せず、適切に処分しましょう。
4.保管方法に注意
- 子どもの手の届かない場所で、直射日光や高温多湿を避けて保管しましょう。冷蔵庫保存が必要な薬もあります。
5.無理強いしない
- どうしても飲んでくれない場合は、無理強いせず、かかりつけ医や薬剤師に相談しましょう。別の味の薬や、形状の違う薬に変更してもらえることもあります。
まとめ:薬は、親子の「信頼」で飲ませるもの
子どもの薬の飲ませ方は、親にとって本当に悩ましい問題ですが、それは、親子の信頼関係が試される場面でもあります。
大切なのは、薬を飲ませるテクニックだけでなく、子どもに寄り添い、安心感を与え、親子の信頼関係を築くことです。
あなたのその愛情と忍耐が、お子さんの回復を早める何よりの力になります。このガイドが、あなたの不安を少しでも和らげ、お子さんとご家族の健康を守る一助となれば幸いです。