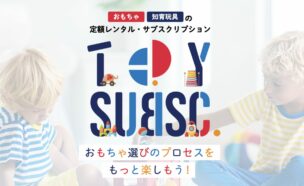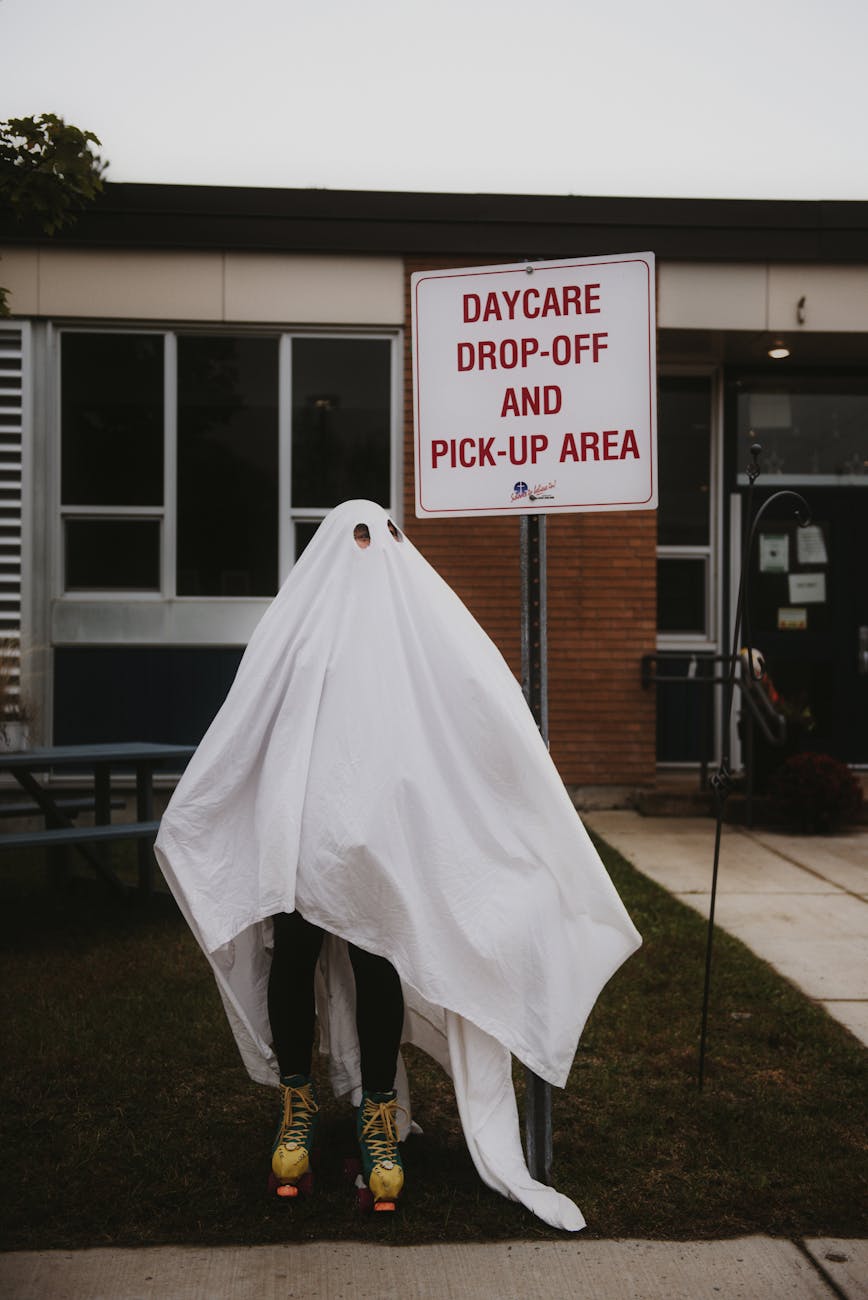「ママ、これ見て!できたよ!」
得意げな顔で、セリアで買った木製パズルを完成させて見せてくれる2歳の娘。こんにちは!3姉妹の母で、現役看護師の皐月です。
最近の100円ショップのおもちゃって、本当にクオリティが高いですよね。特に、セリアやダイソーの知育玩具コーナーは宝の山!我が家でも、娘のお気に入りの木製パズルやシールブックは、ほとんどが100均のものです。
「これで十分じゃない?」「高いおもちゃなんて必要ないよね」
私も、ずっとそう思っていました。娘が楽しそうに遊んでいる姿を見て、100均のおもちゃに何の不満もありませんでした。
…そう、あの日、娘の瞳に「物足りなさ」のサインを見るまでは。
この記事は、100均おもちゃに満足していた我が家が、思い切っておもちゃのサブスク「And TOYBOX(アンドトイボックス)」を試してみた、正直な体験談です。
きっかけは、娘の「もっとやりたい!」というサイン
いつものように、娘は100均の木製パズルで遊んでいました。何度もやっているので、もうすっかりマスターしていて、あっという間に完成させてしまいます。
完成させては崩し、また完成させる。その繰り返しの中で、ふと娘が見せた表情が、いつもの「できた!」という達成感に満ちた顔ではなく、どこか「もう簡単すぎるよ」と言いたげな、少し退屈そうな顔に見えたんです。
その時、ハッとしました。
(この子の「もっと難しいことに挑戦したい」「新しい刺激が欲しい」という成長のサインに、私は応えられているのかな…?)
100均のおもちゃは素晴らしい。でも、子どもの無限の好奇心と成長スピードに、親である私が追いつけていないのかもしれない。そう感じたのが、おもちゃのサブスクを調べてみようと思ったきっかけでした。
なぜ「And TOYBOX」を選んだのか
数あるサービスの中から私がAnd TOYBOXを選んだのは、「LINEでプロのプランナーに相談できる」という点が決め手でした。
「今の娘には、どんなおもちゃが合うんだろう?」
その問いに、素人の私ではなく、保育士資格を持つ専門家が答えてくれる。これほど心強いことはありません。
そして、おもちゃが届いた日…
申し込みから数日後、我が家に大きな箱が届きました。
箱を開けた瞬間、まず驚いたのはおもちゃの質の高さ。自分ではなかなか手が出せない、ヨーロッパ製の美しい木製玩具や、ユニークな知育玩具がぎっしり。100均のおもちゃとは違う、ずっしりとした木の重みと温かみが感じられます。
今回届いたのは、色鮮やかなHape(ハペ)のビーズコースターや、Ed.Inter(エド・インター)の形合わせブロックなど、自分では選ばなかったであろう、でも見るからに質の良いおもちゃたちでした。
娘の目が、見たことのない輝きに
そして、娘におもちゃを見せた時のこと。
娘の目が、今までに見たことがないくらいキラキラと輝いたんです。
特に夢中になったのは、スイス・ネフ社の「ネフスピール」という積み木でした。一見ただの変わった形の積み木ですが、重ね方によって様々な形が作れる、非常に奥の深いおもちゃです。
娘は最初こそ苦戦していましたが、そのうち今まで見せたことのないような集中力でカチカチと組み合わせ始め、30分以上も黙々と遊んでいました。そして、独創的な形が出来上がったときに見せた、あの誇らしげな顔。
100均のパズルを完成させた時の「できた!」とは違う、「自分で考えて、創り出した!」という本物の達成感に満ちた表情でした。
その姿を見て、私は確信しました。
100均のおもちゃが与えてくれる楽しさも本物。でも、プロが選び抜いた質の高いおもちゃは、子どもの中に眠っている新しい可能性を引き出してくれるのだ、と。
結論:「100均」と「サブスク」の併用が最強の選択だった
今回の体験を通して、私は「100均か、サブスクか」という考え方をやめました。
- シールブックや粘土などの消耗品、簡単な遊びは「100均」で
- 発達の核となり、新しい世界を見せてくれる質の高いおもちゃは「And TOYBOX」で
このハイブリッドな使い分けこそ、お財布にも優しく、子どもの成長にも最大限に貢献できる最強の選択だと気づいたのです。
もしあなたが、100均のおもちゃに満足しつつも、心のどこかで「これで十分なのかな?」と感じているなら、一度「And TOYBOX」の世界を覗いてみてはいかがでしょうか。
きっと、お子さんの新しい「好き」や「得意」を発見する、素晴らしいきっかけになりますよ。
より詳しい料金プランや、他の人気サービスとの客観的な比較は、こちらの記事で詳しく解説しています。サービス選びで後悔しないためにも、ぜひ一度目を通してみてくださいね。
▼ 他のサービスとも比べてみたい方はこちら ▼