「ママ、お皿運ぶの手伝う!」
「パパ、はい、新聞どうぞ!」
子どもが、ふと優しい行動を見せてくれた時。
「わぁ、ありがとうね!」
「はい、どうもー」
…あなたは、どんな風に「ありがとう」を伝えていますか?
もしかしたら、日々の忙しさの中で、つい反射的に、一言だけで済ませてしまっていることもあるかもしれません。(ドキッ! 正直に白状すると、私もです…反省。)
もちろん、「ありがとう」と伝えること自体が素晴らしい第一歩!でも、もし、その一言にほんの少し”具体性”をプラスするだけで、子どもの自己肯定感や「またやりたい!」という意欲が、もっともっと育まれるとしたら…?
こんにちは!湘南で子育て中の、3姉妹の母で現役看護師、「こそだて部」の皐月です。
今回の「#ワンポイント育児」では、この「”具体的に”感謝を伝えること」に焦点を当て、
- なぜ「具体的なありがとう」が、子どもの心に深く響くのか?
- 毎日の生活で使える!「伝わる感謝」の伝え方【3つのステップ】
- 我が家での「ありがとう」の伝え方ビフォーアフター
について、具体的な声かけ例や、看護師としてのコミュニケーションの視点も交えながら、お伝えしていきます。
今日から使える、親子の心に温かい循環を生み出すヒント、ぜひ見つけてくださいね!
なぜ「具体的に」が効くの? ”心に響く”感謝の秘密
「ありがとう」だけでも嬉しいけれど、「〇〇してくれて、ありがとう!」と具体的に言われると、大人だって「ちゃんと見ててくれたんだな」って、嬉しさが倍増しますよね。子どもにとっては、その効果はさらに絶大なんです!
1. 自分の”行動”が認められた!【有能感UP】
ただ「ありがとう」と言われるよりも、「テーブルを拭いてくれて、ありがとう!」と言われた方が、子どもは「自分がやった『テーブルを拭く』という行動が、役に立ったんだ!」と具体的に認識できます。これが、「自分はできるんだ!」という有能感(自分には能力があるという感覚)に繋がり、自信を育みます。
2. 「役に立てた!」喜びと意欲【貢献感・やる気UP】
さらに、「〇〇してくれて、助かったよ!」「きれいになって嬉しいな!」のように、自分の行動が相手(親)にどんな良い影響を与えたかが分かると、「自分は人の役に立てる存在なんだ!」という貢献感が満たされます。この「役に立てた!」というポジティブな経験が、「またお手伝いしたい!」「もっと喜んでもらいたい!」という内発的なやる気(モチベーション)を引き出す強力なエンジンになるのです。
3. 親の”見てるよ”サイン【安心感・自己肯定感UP】
具体的に感謝を伝えることは、「ママ(パパ)は、私のやったことを、ちゃんと見て、分かってくれている」という、子どもにとって非常に重要なメッセージになります。自分の行動や存在が、大切な親に承認されていると感じることは、「自分はこのままでいいんだ」という自己肯定感の根っこを、しっかりと育ててくれます。
4. ”感謝の気持ち”が伝わりやすい【コミュニケーション円滑化】
「ありがとう」という言葉に、具体的な行動や気持ちを添えることで、感謝の度合いや理由がより明確に伝わります。「あ、ママは本当に助かったんだな」「パパは本当に喜んでくれてるんだな」と、言葉の重みが増すんですね。また、親が具体的に感謝を伝える姿は、子ども自身が「感謝の気持ちはどうやって伝えたらいいか」を学ぶ、最高のお手本にもなります。
皐月’s Point: 看護の現場でも、患者さんに「〇〇(具体的なケア)をしたことで、少し楽になりましたか?」と具体的に尋ねたり、「〇〇にご協力いただけて、とても助かりました、ありがとうございます」とお伝えしたりすることで、より良いコミュニケーションと信頼関係が生まれます。具体性は、相手への敬意と関心の表れでもあるんですね。
やってみよう! ”伝わる”感謝の伝え方【3つのステップ】
難しく考える必要はありません!いつもの「ありがとう」に、ちょっとだけ言葉をプラスするだけです。
ステップ1:「ありがとう」+”具体的な行動”
- やり方: まずは、「ありがとう」の後に、子どもが「何をしてくれたのか」を具体的に付け加えます。
- 「ありがとう、靴を揃えてくれて」
- 「ありがとう、弟(妹)に絵本を読んであげてくれて」
- 「ありがとう、静かに待っていてくれて」
- 「ありがとう、元気な挨拶をしてくれて」
- ポイント: 大げさなことでなくてもOK!日常のささやかな行動にこそ、具体的に注目してあげましょう。
ステップ2:”気持ち”や”助かったこと”をプラス
- やり方: ステップ1の言葉に、親の気持ちや、どんな風に助かったかを付け加えます。
- 「ありがとう、テーブルを拭いてくれて。ピカピカになって、ママ嬉しいな!」
- 「ありがとう、靴を揃えてくれて。玄関がスッキリして気持ちいいね!」
- 「ありがとう、静かに待っていてくれて。おかげで電話に集中できたよ、助かった!」
- 「ありがとう、元気な挨拶をしてくれて。こっちまで元気が出たよ!」
- ポイント: I(アイ)メッセージ(「私は~」が主語)で伝えると、より気持ちが伝わりやすいですね。
ステップ3:笑顔とアイコンタクトも忘れずに!
- やり方: 言葉をかける時は、しっかり子どもの目を見て、笑顔で伝えましょう。
- ポイント: 言葉だけでなく、温かい表情や態度が、感謝の気持ちを何倍にもして伝えます。
【ボーナスのヒント】
良いことをした時だけでなく、普段の何気ない存在に対しても、「〇〇ちゃんがいてくれるだけで、ママは毎日楽しいよ、ありがとうね」と伝えてあげるのも、自己肯定感を育む上でとても効果的です。(→「どうせ私なんて…」の記事も参考に![※内部リンク想定])
我が家の「ありがとう」の伝え方を変えてみたら…
我が家の三姉妹も、小さい頃からお手伝いは(気分次第ですが…笑)してくれていました。以前は私も、「ありがとう、助かるわー」と、やや定型句のように言うことが多かったんです。
でもある時、長女が食後に自分の食器をキッチンまで運んでくれた時に、意識して「〇〇(長女の名前)、食器を運んでくれてありがとう!ママ、すごく助かったよ!」と、目を見て、笑顔で伝えてみたんです。
そしたら、長女は一瞬キョトンとした後、「…へへっ」と、ものすごーく嬉しそうな、誇らしげな顔をしたんです! その表情を見て、「あ、ちゃんと伝わった!」「『ありがとう』だけじゃ、この笑顔は見られなかったかも!」と、私自身がハッとさせられました。
それ以来、できるだけ具体的に伝えるように意識していますが、やはり「具体的に褒められた(感謝された)」時の子どもの嬉しそうな顔は、格別だなと感じます。そして、そんな時は、次もまた意欲的に手伝ってくれることが多い気がします。(もちろん、いつもではありませんが!笑)
まとめ:”具体的ありがとう”で、親子の心に温かい循環を
「ありがとう!」
その一言だけでも、もちろん気持ちは伝わります。でも、そこに
「〇〇してくれて」 という具体的な行動
「助かったよ!」「嬉しいな!」 という親の気持ち
をプラスするだけで、その言葉は、子どもの自信を育て、やる気を引き出し、「自分は役に立つ存在なんだ」という温かい感覚(自己肯定感)を育む、魔法の言葉に変わります。
特別なことではありません。いつもの「ありがとう」を、ほんの少しだけ具体的にしてみる。
その小さな習慣が、親子の心に、感謝と喜びの温かい循環を生み出してくれるはずです。
完璧じゃなくて大丈夫。まずは今日、何か一つ、お子さんの行動に「具体的ありがとう」を伝えてみませんか?
「こんな『具体的ありがとう』を伝えたら、子どもがこんな反応をしました!」「我が家の感謝の伝え方ルール」など、あなたの体験談やアイデアも、ぜひコメントで教えてくださいね!
「#ワンポイント育児」のヒント、参考になったら、いいね!やシェアをお願いします♪
次回の「#ワンポイント育児」もお楽しみに!







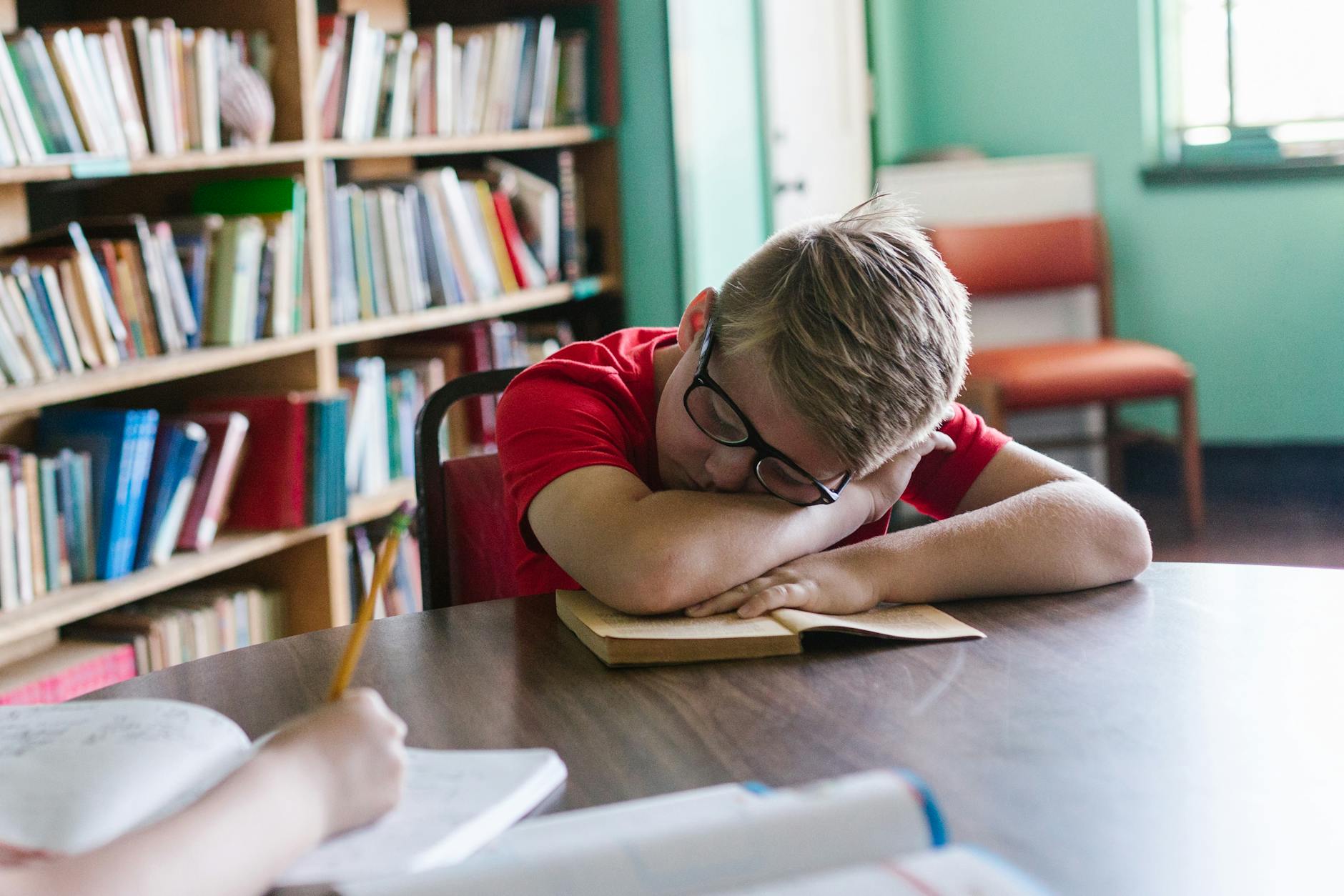
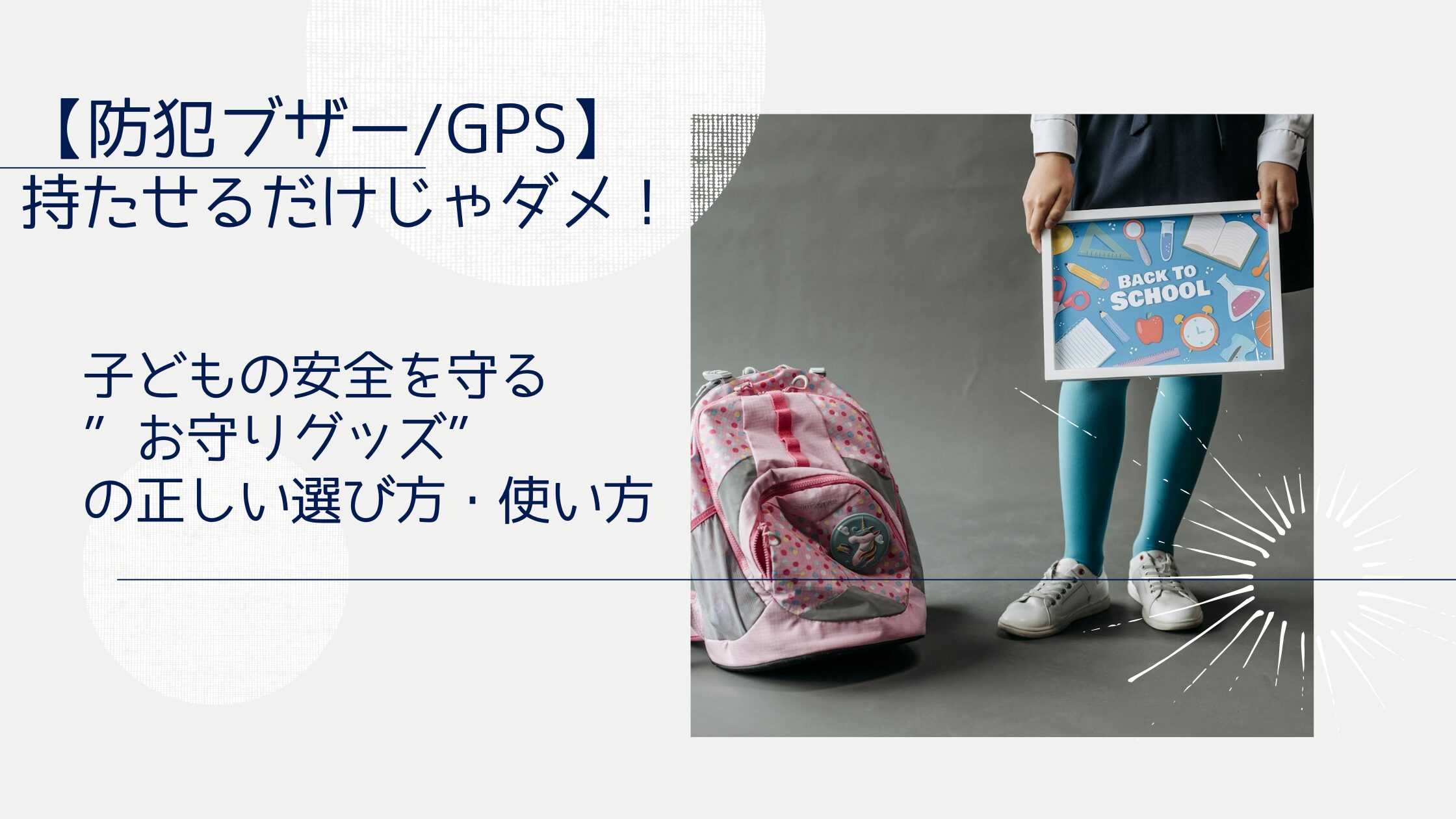
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47049857.275d23fb.47049858.c4fa33ac/?me_id=1383523&item_id=10004906&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flebenwood%2Fcabinet%2F08503648%2F08888872%2F11407399%2F1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)












