こんにちは!3姉妹ママで現役ナースの皐月です。「こそだて部」ブログへようこそ!
「ChatGPT」や「Midjourney」など、最近、すごいAIが登場していますよね!
文章を作ったり、絵を描いたり、まるで魔法みたい…!
「うちの子にも、使わせてみようかな?」
と、思っている方もいるかもしれません。
でも、ちょっと待って!
生成AIは、とても便利なツールですが、子どもが使うには、注意すべき点 もいくつかあるんです。
「えっ、そうなの?」「何に気を付ければいいの?」
と、不安になったあなた。
大丈夫!
この記事では、
- 生成AIを子どもに使わせる際の注意点
- 安全に利用するための具体的な方法
を、ママナースの視点から、分かりやすく解説していきます。
知っておきたい!生成AIの「光」と「影」
生成AIは、使い方次第で、子どもの
- 創造力
- 学習意欲
- 情報収集能力
などを、大きく伸ばしてくれる可能性があります。
でも、その一方で、
- 倫理的な問題
- 様々なリスク
も潜んでいることを、忘れてはいけません。
生成AIの「光」の部分 (メリット)
- 創造性を刺激する:
- 文章、画像、音楽など、様々なコンテンツを生成できる
- アイデア出し、創作活動のサポート
- 学習をサポートする:
- 調べ学習、宿題のヒント、外国語学習など
- 個別最適化された学習 (AIが、子どものレベルに合わせて問題を出題するなど)
- 情報収集を効率化する:
- 知りたい情報を、素早く、簡単に見つけられる
- コミュニケーションを促進する:
- 多言語翻訳、チャットボットなど
生成AIの「影」の部分 (デメリット、リスク)
- 倫理的な問題:
- 著作権侵害: AIが生成したコンテンツが、既存の作品の著作権を侵害する可能性がある
- フェイクニュース: AIが生成した偽情報が拡散される可能性がある
- 差別、偏見: AIが学習データに基づいて、差別的な表現や偏見を含むコンテンツを生成する可能性がある
- リスク:
- プライバシー侵害: 個人情報が漏洩する可能性がある
- 依存症: 過度な利用により、依存症になる可能性がある
- 思考力低下: AIに頼りすぎると、自分で考える力が育たない可能性がある
- 誤った情報: 事実とは異なる情報を信じてしまう。
要注意!子どもが生成AIを使う際の5つの注意点
では、子どもが生成AIを使う際、具体的にどんなことに注意すれば良いのでしょうか?
5つのポイントにまとめました。
1. 年齢制限を確認!
多くの生成AIツールには、年齢制限があります。
例えば、ChatGPTは、13歳以上 (保護者の同意があれば13歳未満も利用可能) となっています。
年齢制限は、必ず守りましょう。
2. 利用時間、利用内容を制限!
- 利用時間:
- 年齢や発達段階に合わせて、利用時間を決める (例: 小学生は1日30分〜1時間)
- タイマーを使って、時間を守る
- 利用内容:
- 教育的な目的、創造的な活動など、利用目的を明確にする
- 有害なコンテンツ (暴力的な表現、性的な表現、差別的な表現など) を含まないか、親が確認する
- フィルタリング機能を活用する
3. 個人情報を入力させない!
- 氏名、住所、電話番号、メールアドレス、学校名など、個人情報を入力させない
- 個人情報が特定できるような写真、動画などをアップロードさせない
- SNSなど、不特定多数の人が閲覧できる場所に、個人情報を書き込ませない
4. 著作権について教える!
- AIが生成したコンテンツは、著作権で保護されている場合があることを教える
- AIが生成したコンテンツを、勝手に利用 (公開、販売など) しないように教える
- 参考にした情報源を明記する
5. 親が一緒に使い、見守る!
- 子ども任せにせず、親が一緒に生成AIを使う
- どんなことに興味があるのか、どんな使い方をしているのかを把握する
- 困ったことがあれば、いつでも相談できる関係性を築く
- AIが出した答えを鵜呑みにしないように、一緒に考える
【ママナース皐月からのアドバイス】
「AIは、あくまでツール。使うのは人間」
ということを、子どもにしっかり伝えましょう。
そして、
- 自分で考える力
- 情報を正しく判断する力
- 批判的思考力 (クリティカルシンキング)
を育むことが、AI時代を生きる子どもたちにとって、何よりも大切だと、私は考えています。
具体例で解説!生成AIのリスクと対策
ここでは、生成AIを使う際に起こりうる具体的なリスクと、その対策を解説します。
ケース1: フェイクニュース
- リスク: AIが生成した偽情報 (フェイクニュース) を信じてしまう
- 対策:
- 情報源を確認する (信頼できる情報源かどうか)
- 複数の情報源を比較する
- AIが出した情報を鵜呑みにしない
- 親子で、フェイクニュースについて話し合う
ケース2: 著作権侵害
- リスク: AIが生成したコンテンツが、既存の作品の著作権を侵害していることに気づかず、公開してしまう
- 対策:
- AIが生成したコンテンツを公開する前に、類似の作品がないか確認する
- 著作権フリーの素材を使う
- 参考にした情報源を明記する
ケース3: プライバシー侵害
- リスク: 個人情報が漏洩する
- 対策:
- 個人情報を入力しない
- 個人情報が特定できるような写真、動画などをアップロードしない
- SNSなど、不特定多数の人が閲覧できる場所に、個人情報を書き込まない
- プライバシー設定を確認する
まとめ|生成AIは「諸刃の剣」!賢く使って、子どもの未来を豊かに
生成AIは、使い方次第で、子どもの成長を大きく後押ししてくれる、素晴らしいツールです。
しかし、その一方で、様々なリスクも潜んでいます。
大切なのは、
- 親が、生成AIについて正しく理解すること
- 子どもに、適切な使い方を教えること
- 一緒に学び、一緒に成長すること
です。
生成AIを「諸刃の剣」として、賢く使いこなし、子どもの未来を豊かにしていきましょう!
まずは、
「生成AIについて、家族会議」
を開いてみませんか?
きっと、新しい発見があるはずです!



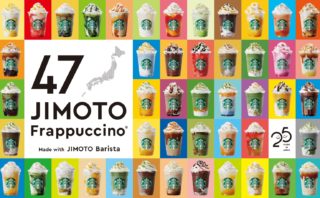










コメント